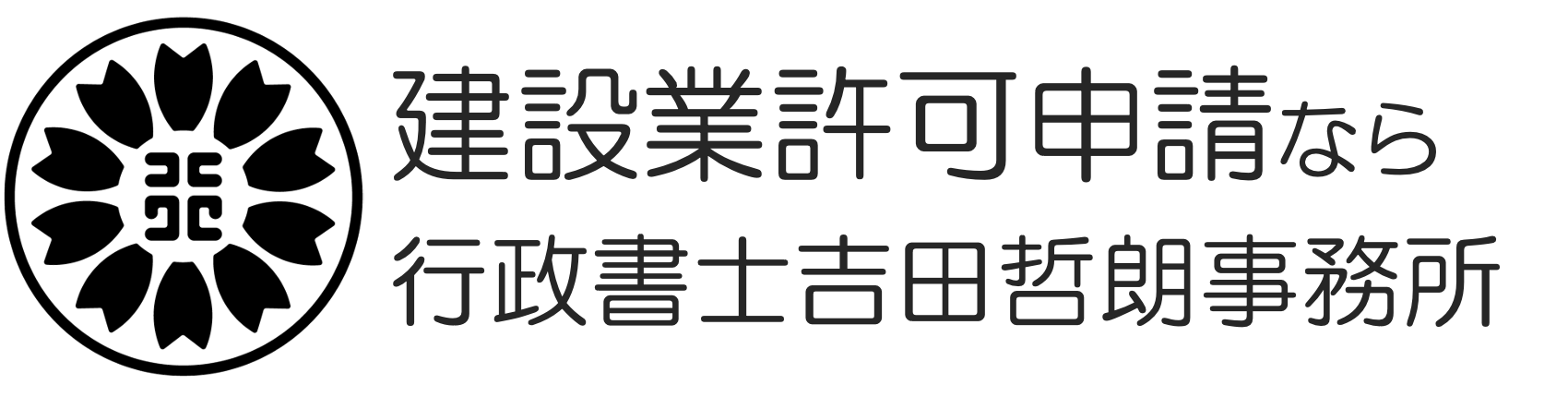・共同企業体の権利主体性は、権利に係る分野で広く認められています。
共同企業体
・共同企業体は法人格を有しない団体(民法上の組合)であるため、共同企業体として行った法律行為の権利義務は、原則として各構成員に帰属し、共同企業体に帰属するためでないと考えらています。
そのため、共同企業体が第三者と法律行為(下請契約の締結、資機材の購入契約の締結、火災保険契約の締結等)を行うには、常に構成員全員の名義を表示するのが原則です。
代表者制度
・共同企業体の外部関係について共同企業体を代表する権限が与えらている代表者制度を設けている場合でも、共同企業体構成員全員の名義を表示したうえで代表者の名義を表示して法律行為を行うことになります。
しかし、共同企業体が建設工事の完成という目的を達成するために行う法律行為すべてが、常に全構成員の表示がないと共同企業体としての権利義務、つまり全構成員の権利義務にならないのでは、実務上不便な場合があります。
共同企業体の法律行為
・共同企業体の法律行為として、全構成員の表示を必要とする方法以外の他の方法による共同企業体の権利主体性が認められるかが問題となります。
・法人格を有する団体は属人的な権利を除き、全ての面で権利主体性が認めらています。
共同企業体の権利主体性が認められる範囲
・共同企業体の権利主体性が認められる範囲は、私的自治の原則が働く余地の大きい権利の分野で広く認められます。しかし、一方、私権を制限する義務の分野ではほとんど認められないと考えられています。
・これに対して、建設業法の許可は、建設工事を営む者に対して、一定の要件を満たす場合に限り同法の許可を認めるものであり、その許可は、実質的な施工主体に対して行うこととなります。このため、各構成員がそれぞれ各会社の内容に応じた許可を受けている必要があります。また、税法上では共同企業体の施工により得た利益については、その分配を受けた各構成員に対して課税されています。
このように、共同企業体の権利主体性は、とくに権利に係る分野で認められています。
投稿者プロフィール

最新の投稿
 お役立ちコラム2026年1月26日不当に低い請負代金とは何か
お役立ちコラム2026年1月26日不当に低い請負代金とは何か お役立ちコラム2026年1月25日著しく短い工期の禁止とは何か
お役立ちコラム2026年1月25日著しく短い工期の禁止とは何か お役立ちコラム2026年1月24日建設工事標準請負契約約款とは何か
お役立ちコラム2026年1月24日建設工事標準請負契約約款とは何か お役立ちコラム2026年1月23日監理技術者資格証とは何か
お役立ちコラム2026年1月23日監理技術者資格証とは何か