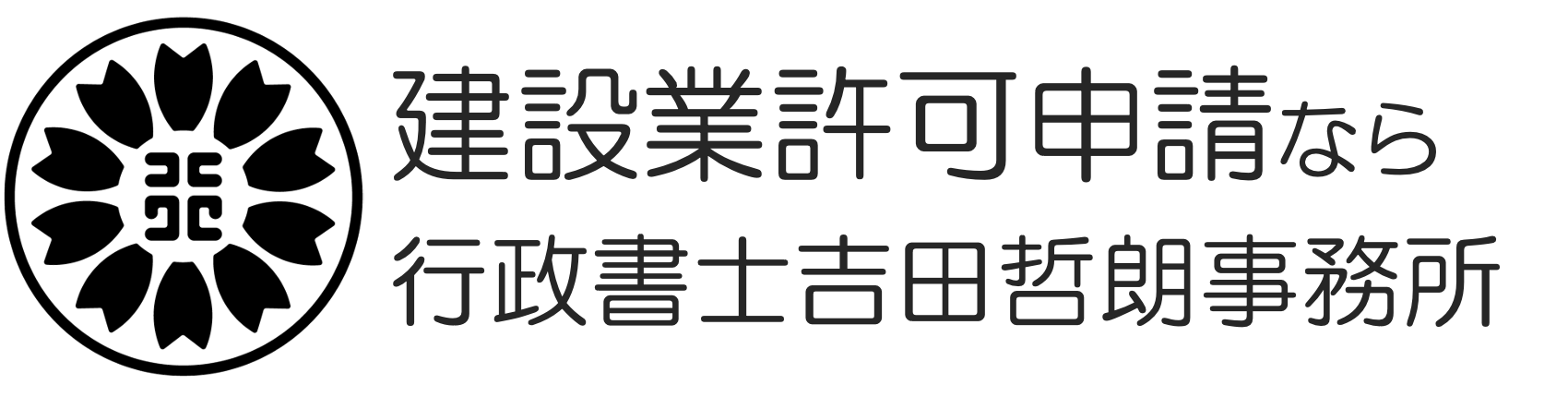建設業法の目的
建設業法は、建設業法を営む者の資質向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としています(建設業法1条)。
すなわち、建設業法の第1の目的は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護することであります。
また、第2の目的は建設業の健全な発達を促進することです。そして、その目的を達成するための手段として建設業を営む者の資質の向上や建設工事の請負契約の適正化が示されています。
建設業法の適用範囲
建設業法は、建設工事の完成を請け負うことを営業とする者に適用されます。
なお、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業許可の適用は除外されますが、原則として建設業法の適用対象とされます。
建設業法の制定、改正
建設業法は昭和24年に制定されました。
それ以来、時代の要請に応えて、数回にわたる改正が行われ、
特に昭和46年は建設業の許可制の採用、請負契約の適正化を中心とする大改正が行われました。
昭和 62 年には、
・特定建設業の許可基準の改正
・監理技術者制度の整備
・技術検定制度 指定試験機関の導入(大臣認定)
・経営事項審査制度の整備
平成 6 年
公共工事をめぐる一連の不祥事の発生と入札契約制度の改革、一般競争入札の本格的採用等とあわせ、
不良不適格業者の排除の徹底
- 建設業許可要件の強化 欠格事由の強化、許可有効期間は 5 年に
- 経営事項審査制度の改善(一定の工事受注者について義務化)
- 施工体制台帳等の整備
- 監理技術者の専任制の徹底
- 再下請け通知書
そして、最近令和4年には、
・監理技術者の配置及び技術者の専任義務についての基準金額の改正
があります。
投稿者プロフィール

最新の投稿
 お役立ちコラム2026年1月27日やり直し工事とは何か
お役立ちコラム2026年1月27日やり直し工事とは何か お役立ちコラム2026年1月26日不当に低い請負代金とは何か
お役立ちコラム2026年1月26日不当に低い請負代金とは何か お役立ちコラム2026年1月25日著しく短い工期の禁止とは何か
お役立ちコラム2026年1月25日著しく短い工期の禁止とは何か お役立ちコラム2026年1月24日建設工事標準請負契約約款とは何か
お役立ちコラム2026年1月24日建設工事標準請負契約約款とは何か